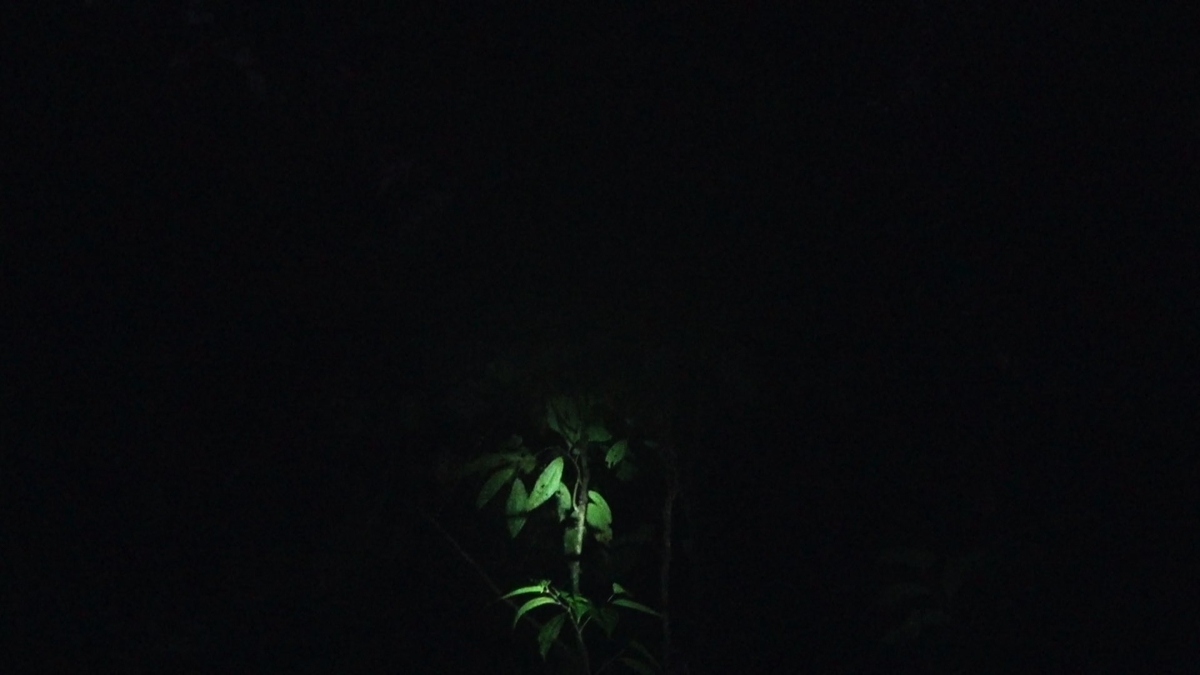陸前高田の、とおい未来のこどもたちにも見てほしい

@realtokyocinema2020
小森はるか監督へのインタビューは、長編デビュー作『息の跡』から3年半ぶりとなる。最新作『空に聞く』は、COVID-19で世界がひっくり返る寸前の、第12回恵比寿映像祭(「時間を想像する」)の東京プレミア上映を幸いにも観ることができた。満席の映像祭のホールで、タイトルにこめた思いを語るQ&Aの小森さんの声に観客はじっと耳を傾けていた。東日本大震災後に、アーティストの瀬尾夏美さんとともにボランティア活動のために岩手に移住し、現地でアルバイトをしながら映画を作りはじめた。最初から“まち”に受け入れられたわけではない。少しずつ、少しずつ、居場所を見つけ、人と繋がる努力をしていたころ、陸前高田災害FMのパーソナリティ、阿部裕美さんと出会う。津波の後のかさ上げ工事が進み、まちの姿が変わりゆくなかで、懸命に「声」をつなげようとしていた阿部さんにカメラを向ける、その親密な距離感。ナレーションも音楽もなく、散りばめられた映像の粒子がひとつのエネルギーに静かに集約されていくシークエンスは小森はるか作品の醍醐味だ。「津波の後の風景だったはずが、“復興の前の風景”を撮っていた」と語る言葉が印象深い。ほかにも作品への思いをいろいろと伺った。
聞き手・文:福嶋真砂代

(C)KOMORI HARUKA
■阿部さんはやわらかで凛として、「メディア」になる人
ーー映画の主人公となる陸前高田災害FMパーソナリティの阿部裕美さんのやさしい光に包まれる感覚がしました。まず、阿部さんと小森さんの出会いから教えて下さい。
小森:陸前高田に私が引っ越したのは2012年の4月でした。最初は大船渡でアルバイトをしていたのですが、その頃に知り合った大船渡の災害FMで働いている方に、陸前高田の災害FMに連れて行ってもらいました。2012年の夏だったかと思います。それ以前から陸前高田の災害FMのTwitterをフォローしていて、きめの細かい情報発信を見るたびに、これはよっぽど思いのある人たちがこの災害FMにいるんだろうな、行ってみたいなと思っていました。ラジオ自体は電波の関係で私はあまり聴けてなかったのですが、災害FMの存在感は感じていて、でもその時はまだ阿部さんの存在は知りませんでした。FM局を訪ねると、阿部さんがちょうど出迎えてくれて、「あ、この方がやってるんだ」ってすごく腑に落ちた感じがしました。阿部さんも私たち(小森はるか+瀬尾夏美)のことをTwitter上で知っていてくれて、短い立ち話のなかで「会いたいと思ってました」と言ってくれました。
ーーなんだか運命的ですね。印象はいかがでしたか。
小森:阿部さんの印象は、物腰がやわらかで穏やかで、凛としている方だと初対面の時に感じました。阿部さんに会うと、みなさん同じような印象を持つようです。その時に阿部さんは「メディア(媒介)」になる人なのだろうなと感じました。まちの人たちの間に立って、声をつなげようとされている方だと。

(C)KOMORI HARUKA
ーー阿部さんを撮影したいと、会ってすぐに思ったのですか?
小森:出会ってから半年くらい経った時です。最初から撮りたいという思いはあったのですが、すぐにはとりかかれず、「映画を作るんだ」と自分の中で決心するまで半年かかっていました。「人を撮りたい」と決心した時に、阿部裕美さんと、そして佐藤貞一さん(『息の跡』)のお二人を撮影したいと思いました。なので「佐藤たね屋」さんの撮影とほぼ同時期でした。
ーーその決心するまでの半年間はどんな時間だったのですか?
小森:引っ越して来たばかりで、誰も知り合いもいなくて、地域や、その日常の中に、どうやって入っていったらいいかということだけで精一杯だった時期です。陸前高田は私が住んでいた住田町(気仙郡)から通っていたので、まだどっぷりという感じではなかったんです。
ーーなるほど、そういう微妙な距離感があるんですね。決心してからは、小森さんひとりで撮影を始めたのですか?
小森:はい、ひとりです。「失われてしまったものを忘れないためにどうやって受け渡していくか」ということをされているまちの人たちの記録を映画にまとめたいという思いはあったのですが、このように関係を結んで撮影をすることが可能だったのはお二人でした。
■撮りたくても撮れなかった光景がそこにあった
ーー阿部さんを撮ることで、番組のリスナーや、他のFM番組「舘の沖.com」のみなさんとか、いろんな方と繋がっていきましたね。
小森:なかなか人にカメラを向けることができなくて。というのは、はじめからカメラを持って出会ったのではなくて、大学院生(自身)が移住してきて、お蕎麦屋さんで働きはじめて、それで受け入れてもらい、親戚みたいにつきあってくれた人たちに対して、私がカメラを向けるとなると、被災した人とそれを撮りに来た人、という関係に結び直されてしまうと感じて。そうではなかったかもしれないけれど、自分としてはそれが怖かったんです。そんな気持ちがありましたが、阿部さんが関わっているラジオの収録の場面では、カメラを向けることが出来たんです。それまで撮りたくても撮れなかった光景がそこにありました。

(C)KOMORI HARUKA
ーー「被写体」としてだけではなくて、扉を開けてくれた出会いでもあるのですね。
小森:扉が開いたんだと思います、ほんとに。ラジオの収録ではあるけれど、映像で記録することを阿部さんも理解してくれたので、撮影に入っても大丈夫な現場に招いてくれました。
ーー「黙祷放送」のシークエンスは圧巻でした。
小森:「黙祷放送」はどうしても撮りたくてお願いしました。地域のみなさんがともに「月命日(毎月11日)に祈る時間」が必要だったのではと思うんです。災害FMで「黙祷放送」をするというのは、ひとりではなく「みんなその時間にいるんだな」と、誰かと一緒に祈る時間を共有するもののように感じられました。弔いの時間のひとつになっていたと思います。

(C)KOMORI HARUKA
■手を撮ることは、顔よりもその人を感じられる
ーー阿部さんが放送局でCDをセッティングしたり、カフを上げ下げしたり、その手仕事を、本業は何をしている方なのだろうと思って見ていました。他にもお弁当を作る手や、お墓参りの手順も整然としていて無駄がない。そしてついに「和食 味彩」ではたらく阿部さんが映され、「阿部さんの手の秘密はこれだったのか」とわかる、そのシークエンスにゾクっときました。
小森:そうなんですね、ぜんぶが繋がってるなと思いました。阿部さんの手の動かし方は生活している人の、プロとはまた違うリズムがあると思いました。人が作業しているところを見ているのが好きです。手を撮るのは、顔よりもその人を感じられると思うからなんです。阿部さんは「ひとつひとつ確認する」というところが手に現れていて、それが阿部さんの性格を表しているように思います。丁寧に、間違えないように、緊張感を持って点検していく感じ。震災前に飲食店で仕事されていたときも、そうやって仕事をされてきたのだろうということが伝わってきて、すごくいいんですね。
ーー阿部さんはこの映画をいつごろ観られたのですか?
小森:愛知芸術文化センターでの上映の前です。観ていただいて、確認作業に長くお付き合いいただきました。阿部さんが気になるところ、誤解がないようにというところを指摘して下さって、そのすべてに私が応えられたわけではないのですが、阿部さんのほうから、「小森さんの表現だから、やりたいようにやったらいいよ」と言って下さって、結局はそのようにやらせていだだきました。
どこまで情報があったほうがいいのか、私自身も迷いがあったし、阿部さんも心配されたところです。本当に伝わるかどうか。例えば黙祷放送のシーンは、最初に原稿を読んでから黙祷をして終了となるのですが、じつは原稿を読んでいるところを私はカットしています。黙祷放送にとってとても大事な部分なので私も迷いましたし、阿部さんもなぜカットするのかと思われたと思うのですが、編集意図を理解して受け入れて下さいました。本当に難しいところですが、迷いはありつつも、やはり自分が観たいものを選びました。手探り状態で撮影をはじめた中で「これだ」というものを自分で見つけていくときに、阿部さんにご意見いただいて、いい意味で自分のやりたい方向を見つけさせてもらったという気がします。

(C)KOMORI HARUKA
■津波の後の風景だったはずが、“復興の前の風景”を撮っていた
ーー2013年冬からのFM局と2018年夏のインタビュー部分と、二つの時間にまたがって撮影をされています。過去に撮影した素材で、時間を隔てて映画にしようと決心した時、気持ちも変化していくのだと思いますが、撮った素材に対しての思いも変化をしていますか。
小森:それはあるような気がします。その時は何も映らないなと思って撮っていた風景が、もはやいまは“失われた風景”になっていたりします。また時間が経てば変わるかもしれないですが、「津波の後の風景だったはずが、復興の前の風景を撮っていた」ということになっていくんです。自分が作品にしようと思うタイミングによって素材の見え方、捉え方が違ってくるし、阿部さんの語りによって、そういうふうに見直せたということはあります。そんなことがこれからもずっと起きるような気がしてます。
ーーコロナ禍でお祭りの在り方も変わってくると、それを映像化して残すことも貴重です。毎回「お祭り」は小森さんらしくて魅了されます。
小森:ほんとですか、お祭りばかり撮るのは卒業しなきゃ(笑)。もし記録係として撮るならいろんなことを定点的に撮っていないとダメですけど、記録をすると言いながらも、私は自分の撮りたいものしか撮っていなくて。せめてそれを何かしらの形で渡したいという時に「映画」という表現方法が今はいちばんしっくりきます。お祭りの意味合いとしても鎮魂の意味がありますし、そこに居なかった人たちが、人が集まることで見えてくる。お祭りによって人の気持ちが可視化されることがあると感じて、その瞬間を見たいと思って撮ってしまうし、編集で入れてしまうんです。

(C)KOMORI HARUKA
ーー「ワッショイ、ワッショイ」の声の被せ方に痺れますし、阿部さんが「“おかえり”の文字が上から見えるような位置に書いてあるんですよ」と話してくれたのも、鳥肌がたちました。現世とあの世をつなぐ、それこそ「メディア」として撮る、小森さんのお祭りは、賑やかさだけではなく、どこか寂しさを感じさせます。
小森:確かにすごく寂しさを感じます。お祭りだけど賑やかだけじゃない。それが伝わるのはうれしいです。
■撮られる側の意識が変わってきている
ーーちょっと話が変わるのですが、いまは高性能スマートフォンカメラがあって、どこでも人は撮影することに抵抗がなくなってきました。映画を撮る状況も、小森さんが映画を撮り始めてから変わってきたのではないでしょうか。
小森:変わっています。撮る側だけではなく、撮られる側の意識もすごく変化しているなと感じます。日常的に撮られる機会が増えて、「映像に映っている自分」を観る機会も増えていますね。昔の人が感じた「写真に魂を抜かれる」恐怖感とは違うんだと思います。特に若い人たちはどういうふうに撮られているかわかって撮らせてくれている感じがして、そういう意味で変わってきたと思います。
『二重のまち/交代地のうたを編む』(制作:小森はるか+瀬尾夏美)の撮影をした時に、初めて陸前高田の高校生を撮らせてもらったのですが、例えばご高齢の方は、カメラに自分がどう映っているかわからないからこそ自然でいてくれることがあります。でも高校生はその逆で、カメラに撮られていることをわかりながら「自然に」居ようとしているなというのが伝わってきて、カメラの前で「振る舞える」ということですね。だからこそ自分も気をつけようと思いました。被写体側がそうやって受け入れてくれることに甘んじないようにしようと。撮らせてくれることに慣れてしまうのは、自分でもちょっと怖いなと思ってます。

(C)KOMORI HARUKA
■陸前高田の、とおい未来のこどもたちへ
ーー最後に、この映画をどのように見てもらいたいでしょうか。
小森:映画を見てくださる方それぞれに、阿部さんの声を聞いて、変化していく陸前高田の風景を見て、何か感じるものが一つでもあれば嬉しいです。あと最近想像するのは、このまちでこれから生まれる人たちは「いまの状況」は見れないだろうなということです。震災の記録は多く残っているし、津波や被害の様子などは資料館にもあります。でも復興していくまでの時間の人々の複雑な思い、例えば阿部さんがラジオのパーソナリティをしていた時間や、佐藤(たね屋)さんが井戸を掘っていた時間、という記録はなかなか出会えないと思うんです。だから、それを次に渡したいという気持ちがあります。自分がもしそこに生まれたとしたら、そういう人たちがいたことを知りたいと思うだろうな、と。いまに至るまでに間をつないでいた人たちを誰かに伝えたいという思いがあって、記録しているのだと思います。陸前高田でそれを必要とする世代はもっともっと先のことかもしれない。おじいちゃんやおばあちゃんからその話を聞けるという世代はまだ大丈夫ですけど、そのもっととおい未来のこどもたちがいつか見るものであったら、という思いもあります。
(※このインタビューは、2020年10月16日に行われました。)
11月21日(土)より東京 ポレポレ東中野にて公開、ほか全国順次公開
Information:
監督・撮影・編集:小森はるか
撮影・編集・録音・整音:福原悠介
特別協力:瀬尾夏美
企画:愛知芸術文化センター 制作:愛知県美術館
エグゼクティブ・プロデューサー:越後谷卓司
配給:東風 2018年/日本/73分
www.soranikiku.com
関連記事