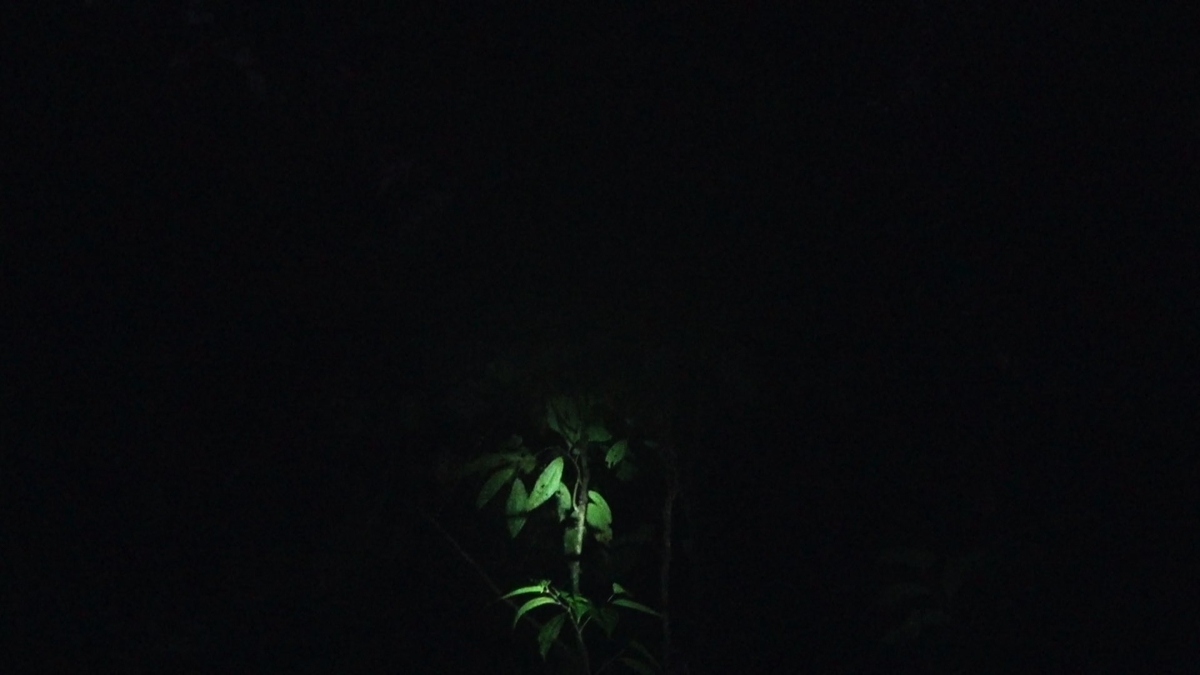新年恒例のREALTOKYO CINEMA (RTC)の「CINEMA10」(シネマテン)は5回目になりました。おなじみのメンバー7名(澤隆志、石井大吾、松丸亜希子、前田圭蔵、白坂由里、フジカワPAPA-Q、福嶋真砂代:原稿到着順)が、2020年に観た映画からそれぞれ選ぶ推しの10本。あえて鑑賞形態、公開年、ジャンルにもこだわることなく幅広くセレクトしました。たとえパンデミックな世界でも、「映画」という共通言語でつながれることの喜びを強めに確認しつつ、今年も全力で「多様な視点」重視の個性滲みでるバラバラ感「OK!」(今年のメインビジュアル/ナウシカ)でお届けします。お楽しみ下さい。ということで、2021年もRTCをよろしくお願いいたします。
<2020 RTC CINEMA10>
★澤 隆志の2020 CINEMA10
コメント:covid-19が収まらないのに年末気分になれる? と思いウィズコロナ真っ只中の10本というセレクト。思い出し順。配信リンク(→)があるものは併記したので2021に再見可。世界が同時に止まる経験は後にも先にもないだろう。経済が止まる。と、デスマーチも止まるわけで、落ち着いて自己を省みる時間ができた人も多かったように感じる。世論が動いたり集団提訴が起こったりアクションできなくて鬱になったり。個人と社会の薄くて厚い壁を描いた作品が強く心に残った。仕掛けの豊富な「Sai no Kawara」はドキュメンタリー映画として最も沁みた作品!

- 『Sai no Kawara』https://www.youtube.com/watch?v=rmeI_Qk1rrk
- 『その手に触れるまで』http://bitters.co.jp/sonoteni/
→https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B08QGW2CGN/ - 『フェアウェル』http://farewell-movie.com/
- 『ミークス・カットオフ』https://gucchis-free-school.com/event/kelly01/
- 『山の焚火』https://gnome15.com/mountain/
→https://tsutaya.tsite.jp/item/movie/PTA00008C454 - 『妊娠した木とトッケビ』http://www.imageforumfestival.com/2020/program-f
- 『A Day to Remember』A Day to Remember on Vimeo
- 『ポップスター』https://gaga.ne.jp/popstar/
→https://www.amazon.co.jp/dp/B08LDJKH3H - 『レ・ミゼラブル』http://lesmiserables-movie.com/
→https://www.amazon.co.jp/dp/B08P9VKR33/ - 『音楽』http://on-gaku.info/→https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B08KVRQQH9/
★石井大吾の2020年 CINEMA10
コメント:見逃した映画の多い1年でした。あの映画を観ていたら、このリストが入れ替わっているかもしれないと思う映画が何本もあります。しかし、振り返ってみると、こんな状況でも素晴らしい映画はたくさんあるし、映画館があることのありがたさを思います。1本目は『風の谷のナウシカ』をついに劇場で。繰り返されるテレビ放送で、慣れた風景のようでもあるし、本質はコミックの方という気持もありました。それでも1番目に書かざるをえないほど改めて強い印象が残りました。今までいろんな形でこの物語と接してきたからこそ、映画館で映画を観るということの価値が浮かび上がったと言えるかもしれません。夜中、シアターには一人でしたが、マスクを着用して全身で映画に浸りました。あとは、青春映画(と言えばいいのでしょうか)も多いですね…。はたしていつまでキュンとなりながら映画を観ていいものか、観ることができるのでしょうか…。

- 『風の谷のナウシカ』https://www.youtube.com/watch?v=KJgPuDwygXA
- 『行き止まりの世界に生まれて』http://bitters.co.jp/ikidomari/
- 『さよならテレビ』https://sayonara-tv.jp/
- 『佐々木、イン、マイマイン』https://sasaki-in-my-mind.com/
- 『なぜ君は総理大臣になれないのか』http://www.nazekimi.com/
- 『アルプススタンドのはしの方』https://alpsnohashi.com/
- 『セメントの記憶』https://www.sunny-film.com/cementkioku
- 『ようこそ映画音響の世界へ』http://eigaonkyo.com/
- 『ハニーランド 永遠の谷』http://honeyland.onlyhearts.co.jp/
- 『ヴァニタス』https://www.youtube.com/watch?v=dVtdAf1beG8
★松丸亜希子の2020 CINEMA10
コメント:新潟県長岡市に移住して7年目、県内から一歩も出なかった2020年。コロナ旋風が吹き荒れる直前に骨折を初めて経験し、全身麻酔での手術を経て車椅子・松葉杖生活、リハビリに追われた上半期でした。入院中もステイホーム中もネット配信の映画やドラマを観まくりましたが、このラインナップは劇場に足を運んで観た作品を観賞順に並べたもの。11・12月は諸事情でまたもや外出がままならず、各種ハードルがあった中で秀逸な作品群に出合えたことに感謝です。

- 『パラサイト 半地下の家族』http://www.parasite-mv.jp
- 『ミッドサマー』https://www.phantom-film.com/midsommar/
- 『デッド・ドント・ダイ』https://longride.jp/the-dead-dont-die/
- 『MOTHER マザー』https://mother2020.jp
- 『宇宙でいちばんあかるい屋根』https://uchu-ichi.jp
- 『はちどり』https://animoproduce.co.jp/hachidori/
- 『行き止まりの世界に生まれて』http://bitters.co.jp/ikidomari/
- 『星の子』https://hoshi-no-ko.jp
- 『スパイの妻 劇場版』https://wos.bitters.co.jp
- 『朝が来る』http://asagakuru-movie.jp
★前田圭蔵の2020 CINEMA10
コメント:コロナ禍が世界中を覆った2020年。流行語大賞にもなった「三密」回避とソーシャル・ディスタンスの確保が求められ、映画や舞台、音楽にとっても苦しい状況がまだまだ続く。”ステイ・ホーム”の時間が増えはしたが、脚光を浴びることになった配信動画を見る機会は意外と増えなかった。むしろ、少しでも外界と繋がっていたいという欲求がふつふつと湧き上がり、散歩をしたり、自転車で徘徊したりする時にこそ大きな喜びを感じる。2020年の僕のベスト・フィルムは、キム・ボラ監督作「はちどり」。物語も、登場人物も、カメラワークも刺さりまくった。フィルム作品では無いが、大好きなNHKのTV番組「ドキュメント72時間」の「としまえん 日本最古の回転木馬の前で」も泣けました。そして、東京フィルメックス特別企画として上映されたマノエル・ド・オリヴェイラ監督『繻子の靴』を見逃したので、映画館での上映希望です!(リストは順不同)

- 『はちどり』https://animoproduce.co.jp/hachidori/
- 『白い暴動』http://whiteriot-movie.com/
- 『ペイン・アンド・グローリー』https://pain-and-glory.jp/
- 『真夏の夜のジャズ 4K』http://cinemakadokawa.jp/jazz4k/
- 『衝動ー世界で唯一のダンサオーラ』https://impulso-film.com/
- 『ラスト・ブラックマン・イン・サンフランシスコ』http://phantom-film.com/lastblackman-movie/
- 『音響ハウス Melody Go Round』https://onkiohaus-movie.jp/
- 『BOLT』http://g-film.net/bolt/
- 『イヴォ・ヴァン・ホーヴェ演出作品 上映会』東京芸術祭2020』https://tokyo-festival.jp/2020/Ivo_Van_Hove
- 『セノーテ』http://aragane-film.info/cenote/
★白坂由里の2020 CINEMA10
コメント:雲間から光。厄災後の寓話のような『ホモ・サピエンスの涙』には、神を信じられなくなって精神科に通う神父が登場する。「神様が考えてくれないなら、こっちで考えるしかないでしょ」とは『海街diary』の加瀬亮のセリフだが、10本ともそういう映画です(笑)。1)ロイ・アンダーソン、2)中尾広道、3)岩井澤健治の止むに止まれぬ手の仕事に胸熱。規格化への抵抗のよう。5)は仲間のスケートビデオを撮った12年がラストベルトを映す鏡に。『mid90s ミッド・ナインティーズ』とセットで。6)と7)は「声」に耳を傾け、自分で言葉を探す映画。8)は家族への優しい嘘のために履き慣れぬ靴で走るオークワフィナに涙。10)のジョー、そしてグレタ・ガーウィグとシアーシャ・ローナンのコンビに晴れ晴れとした気分に。全体的に、芸術と家族と経済、家族と自分と時間の関係について考えることが多かったです。(リストは順不同)

- 『ホモ・サピエンスの涙』http://www.bitters.co.jp/homosapi/
- 『おばけ』https://wubarosier.tumblr.com/
- 『音楽』http://on-gaku.info/
- 『詩人の恋』https://shijin.espace-sarou.com/
- 『行き止まりの世界に生まれて』http://www.bitters.co.jp/ikidomari/
- 『空に聞く』https://www.soranikiku.com/
- 『春を告げる町』https://hirono-movie.com/
- 『フェアウェル』http://farewell-movie.com/
- 『凱里ブルース』https://www.reallylikefilms.com/kailiblues
- 『ストーリー・オブ・マイライフ 若草物語』https://bd-dvd.sonypictures.jp/storyofmylife/
★フジカワPAPA-Qの2020 CINEMA10
コメント:音楽関連映画。1:ロビー・ロバートソンの自伝を元にした彼等の歴史。2:生演奏もある岩手県一関市の世界的ジャズ喫茶に集うジャズ人。3:ハチャメチャSFコメディ。キアヌ・リーヴスがテルミンを演奏する。4:グレース・ジョーンズ素敵。「リベルタンゴ」が何度も流れる。5:昭和歌謡を歌う、のんが最高!6:マイルス・デイヴィスの真実を歴史的映像、関係者の証言で記録。7:1958年の音楽祭。動くセロニアス・モンク、エリック・ドルフィー等!8:モータウンの初期デトロイト時代の約10年の記録。9:ジョン・ケージやビートルズも登場して驚き。10: REALKYOTOの浅田彰さんの評論で知った。テオドール・クルレンツィスとムジカエテルナのベートーヴェン第九の演奏を中心とした約30分の哲学的記録映像。(リストは題名五十音順)

- 『ザ・バンド かつて僕らは兄弟だった』https://theband.ayapro.ne.jp/
- 『ジャズ喫茶ベイシー Swiftyの譚詩(Ballad)』https://www.uplink.co.jp/Basie/
- 『ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え』https://www.phantom-film.com/billandted/
- 『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』http://helmutnewton.ayapro.ne.jp
- 『星屑の町』https://hoshikuzu-movie.jp
- 『マイルス・デイヴィス クールの誕生』https://www.universal-music.co.jp/miles-davis-movie/
- 『真夏の夜のジャズ 4K』http://cinemakadokawa.jp/jazz4k/
- 『メイキング・オブ・モータウン』http://makingofmotown.com
- 『ようこそ映画音響の世界へ』http://eigaonkyo.com
- 『プランB』https://www.youtube.com/watch?v=TasClnikg0o
★福嶋真砂代の2020 CINEMA10
コメント:大変なコロナイヤーも、振り返ると3月まではコンスタントに試写室のイスを温め、後半オンライン環境に変わっても充実の出会いは続いた。1)はド・ストライクなイーストウッドの真髄みたり。2)の山トリロジー、牧歌的と思ったら急激な不協和音に心がザワつく怪作。3)はダンサオーラインプルソに自分的踊り子ダマシイが疼くのだ。4)はいい意味で“異質な”女優、モトーラ世理奈を発見。 5と7)はドキュメンタリーの底力、両監督インタビューも実り多く。6)は大倉と成田が体当たりする切ない純愛にキュン死、海辺シーンも痺れる。映画の醍醐味とはまさに8と9)のこと。10)は映像の魔術師、ロイ・アンダーソンの凝り凝りの世界が好きすぎる。(リストは鑑賞順)

- 『リチャードジュエル』https://wwws.warnerbros.co.jp/richard-jewelljp/
- 『山の焚き火』https://gnome15.com/mountain/
- 『衝動ー世界で唯一のダンサオーラ』https://impulso-film.com/
- 『風の電話』http://www.kazenodenwa.com/
- 『空に聞く』https://www.soranikiku.com/
- 『窮鼠はチーズの夢を見る』https://www.phantom-film.com/kyuso/
- 『精神0』https://www.seishin0.com/
- 『デッド・ドント・ダイ』https://longride.jp/the-dead-dont-die/
- 『スパイの妻 劇場版』https://wos.bitters.co.jp/
- 『ホモサピエンスの涙』http://www.bitters.co.jp/homosapi/
●選者プロフィール(原稿順)
・澤隆志:2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館などと協働キュレーション多数。「めぐりあいJAXA」(2017-)「写真+列車=映画」(2018)などプロデュース。
・石井大吾:fuse-atelier、blue studioを経て2008年よりDaigo Ishii Designとして活動開始。建築、インテリア、家具などのデザインを手がける。2009-2015年には中野にてgallery FEMTEを運営。 2018年からは株式会社アットカマタの活動にも参加している。2019年、京急梅屋敷にKOCA(koca.jp)をオープン。https://www.daigoishii.com/
・松丸亜希子:1996年から2005年までP3 art and environmentに在籍した後、出版社勤務を経てフリーの編集者に。P3在職中に旧REALTOKYO創設に携わり、2016年まで副編集長を務める。2014年夏から長岡市在住。
・前田圭蔵:世田谷美術館学芸課を経て、80年代後半より音楽やコンテンポラリー・ダンスを中心に舞台プロデュースを手掛ける。F/T11、六本木アートナイト、あいちトリエンナーレ2013パフォーミング・アーツ部門プロデューサーなどを歴任。現在は東京芸術劇場に勤務。旧realtokyo同人。
・白坂由里:神奈川県生まれ、小学生時代は札幌で育ち、現在は千葉県在住。『WEEKLYぴあ』を経て1997年からアートを中心にフリーライターとして活動。学生時代は『スクリーン』誌に投稿し、地元の映画館でバイトしていたので、いまも映画に憧れが……。
・フジカワPAPA-Q:選曲家、DJ、物書き、制作者等。NHK-FMのゴンチチさんの番組「世界の快適音楽セレクション」選曲構成。コミュニティ放送FM小田原の番組制作者として、巻上公一さん等の番組担当。フジロックで開催のNO NUKESイベント「アトミックカフェ・トーク&ライブ」(MCは津田大介さん)制作。等々色々活動中。
・福嶋真砂代:RTC(REALTOKYO CINEMA )主宰。航空、IT、宇宙業界を経てライターに。『ほぼ日刊イトイ新聞』の「ご近所のOLさんは、先端に腰掛けていた。」などコラム寄稿(1998-2008)。黒沢清、諏訪敦彦、三木聡監督を迎えたトークイベント「映画のミクロ、マクロ、ミライ」コーディネーター&MC(2009)。旧Realtokyo(2005年から)と現RealTokyoにも寄稿。